
ポスト・スマートシティ 第4回 わが国における公共交通・MaaSの進む道 ~持続可能な移動手段の確保に向けて~
情報センサー2020年12月号 パブリックセクター
インフラストラクチャー・アドバイザリーグループ
公認会計士 長谷川太一
2000年当法人入所後、会計監査や民間企業向け財務アドバイザリー業務を経験後、05年より現職。省庁・自治体、民間企業等向けに空港、水道、公共交通、都市開発等のPPP/PFI事業に関するアドバイザリー業務を担当。インフラ分野のコンセッション事業等、「官」と「民」の境界を再定義する事業に多数従事している。当法人 パートナー。
Ⅰ はじめに
第1回(本誌2020年7月号)において、ポスト・スマートシティ時代におけるサステナブルシティの在り方について整理しました。その中で、サステナブルシティの実現に向けてはパブリック・ガバナンスが必須要件であり、これらは全体最適の視点、ステークホルダー間の利害調整を担う司令塔組織、調達・PPP(Public Private Partnership:官民連携)の在り方などを含むと整理しました。そこで本稿では、これらの視点を基に、公共交通をテーマにサステナブルシティの在り方を考えてみたいと思います。
Ⅱ わが国における公共交通政策の難しさ
公共交通を移動手段の主役と位置付け、またMaaS(Mobility as a Service)の先進地とされる欧州に比べて、わが国では同様の検討を行うのは非常に難しいとされています。その要因はどこにあるか、考察していきます。
一つ目は、公共交通の司令塔機能の欠如にあると考えます。わが国では公共交通が民間私鉄等の都市開発を伴う経済成長とともに歩んできた経緯があるため、交通モードの統合には各社の利害調整が必要となり、一筋縄ではいかない背景があります。これに対し、ドイツ等の欧州では、地域公共交通は制度的に公共サービス義務(PSO:Public Service Obligation)が課せられるものと定義付けられており、州や市などの自治体が司令塔となって運営されているため、定額制料金まで含め複数サービスの統合を行いやすい素地があります。二つ目は、オープンデータの欠如にあると考えます。これも一つ目と同様で、欧州では公共主導で交通機関のオープンデータ化が進められていましたが、わが国では交通データの多くを民間事業者が個別に保有している上に、JR東日本のSuicaデータのオープン化の議論のように、個人の移動・利用情報のオープン化への国民の抵抗感も大きいといえます。
1. 地域公共交通の役割分担の再定義
今、コロナ禍を受けて、多くの地域公共交通事業者は極めて厳しい危機に直面しています。コロナ禍以前は少子高齢化や人口減少の影響を、急増するインバウンド需要を取り込むことで何とか穴埋めし、地方鉄道や路線バスなど地域住民の足を維持してきました。しかし、インバウンドの回復は、IATA(国際航空運送協会)の試算によれば、航空需要がコロナ禍以前(2019年)の水準に戻るのは、2024年になるとの見通しであり不透明な状況です。足元では、埼玉の路線バス事業者や大阪のタクシー会社で倒産事例が出ており、長野県松本市では路線バスの公設民営の議論が沸き起こっています。このように、地域公共交通はそもそも構造的に赤字事業で、民間の商業事業として維持することはほぼ困難な状況がコロナ禍により浮き彫りになったといえます。
他方、ドイツなどでは、公共交通のうち都市間交通は商業サービス、地域公共交通は公共サービス義務と位置付け、自治体が責務を負って、自治体財源を活用し運営されています。また、運輸連合という地域公共交通の司令塔を担う組織(州政府や市町村および交通事業者の出資団体)が設置されており、地域の路線網、料金、運行ダイヤなどの戦略・計画は公共責務で策定されています。
このコロナ禍を契機に、わが国地域公共交通の公益性とは何か、何を残すべきか、残す場合は誰の責務で誰の負担で残すのか、地域公共交通の役割分担の再定義を真正面から議論すべき時期を迎えているといえます。
2. 交通データのオープン化
前述のように、わが国では個人の移動データ含む交通データのほとんどは民間事業者が保有しているため、民間事業者の判断とリスクでオープン化を促進させるのは実務上難しいといえます。もちろん、国土交通省でも「MaaS関連データの連携に関するガイドラインver.1.0」を整備し、MaaS関連事業者のデータ提供を促していますが、判断は個々の民間事業者に委ねられているため、どこまでデータ蓄積が進むかは不確実な状況です。
例えば、ヘルシンキ市では、MaaS導入以前から、環境政策と関連させて、公共交通の分担率を向上させる取り組みとして、行政主導で交通機関の利便向上に向けたオープンデータ化を進めていた経緯があり、それがMaaSの発展に大きく寄与したといわれています。
このように複数の交通モードの統合を含むMaaSを成功させるには、移動情報を含む交通データのオープン化は重要な前提条件になります。
Ⅲ わが国におけるMaaSの現状
次にわが国MaaSの現状に目を向けたいと思います。今、全国各地でスマートシティの検討が進んでいますが、移動やMaaSは住民サービスの維持・向上の点から外せない分野として議論されています。しかし、そこで語られるMaaSやスマートモビリティの議論に少し違和感を抱くときがあります。
本来、MaaSとは複数のモビリティサービスがICT等で統合され、あたかも一つのサービスとして利用可能なシームレスな状態を指す概念をいいます。<図1>上段の「①複数の交通モードの統合」がこれに当たり、いわゆる"狭義"のMaaSといえます。これに加え、<図1>下段の自動運転やAIオンデマンドなどの「②新たな移動サービスの導入」や、飲食・娯楽・医療サービスとの組み合わせである「③他業態サービスとの連携」は、統合された移動サービスをさらに向上させるために付加的に組み込まれるものと整理することができます。これら①、②、③を合わせたものが"広義"のMaaSといえます。

この点から見た場合、多くの自治体におけるMaaSやスマートモビリティの議論では、②や③に該当する自動運転、AIオンデマンド、観光セット型MaaSなどの付加的なサービスに焦点が当たりがちで、①に該当するMaaSの"本丸"たる公共交通サービスの統合の議論が置き去りになっているケースが見られます。
これはわが国MaaSの進展状況からもうかがえます。<図2>のとおり、「①複数の交通モードの統合」のレベルは、統合度合いによって四つに区分されますが、レベル2と3の間に大きな"壁"があります。レベル2は予約・決済・情報の統合であるのに対し、レベル3では複数の交通モードの料金が定額料金制などサブスクリプションで統合されている状態をいいます。この料金統合には、事業者間で定額料金の設定や収入の配分ルールを合意する必要があり、わが国ではハードルが高いといわれています。
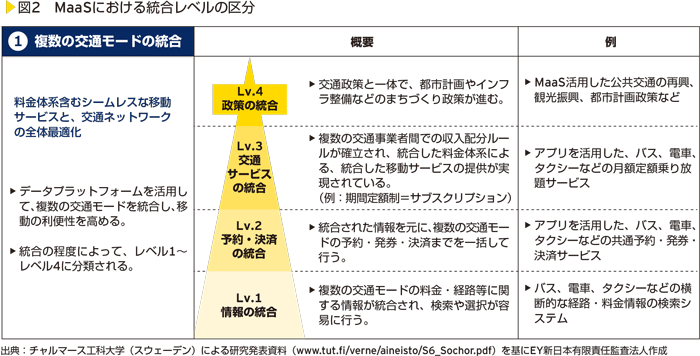
当法人が国内の観光MaaSや生活MaaSの先進事例20以上を分析した限りでは、わが国MaaSのほぼ全てがレベル2に留まっており、完全にレベル3に到達した事例はありませんでした。これは、本丸のMaaS議論よりも、「②新たな移動サービスの導入」や「③他業態サービスとの連携」の議論に焦点が当てられている状況を反映していると考えられます。なお、国内事例の中でも、WILLER社が京都丹後鉄道沿線地域で地域のバス会社やタクシー会社を巻き込んだ実証実験の取り組みや、観光型MaaSの先進事例であるIZUKO(東急等が運営する伊豆地域における観光型MaaS)などは、レベル3を目指した先進的な取り組みといえます。
一方で、海外に目を向けると、フィンランド・ヘルシンキ交通局によるWhimはすでにレベル3に到達しており、またベルリン市交通局がリトアニアのスタートアップTrafi社と組んで進めている統合アプリ「Jelbi」では、レベル3への到達をミッションとしています。実際に同アプリは全ての交通事業者と連携可能な形で設計・制作されています。
Ⅳ おわりに
このようなわが国特有の公共交通政策の難しさを抱えながらも、地域が自ら公共交通の在るべき姿や、地域に最適なMaasの活用策を真正面から検討し始めている事例も出てきています。
例えば、前述のWILLER社の京都丹後地域でのMaaS事例の背景には、2015年の北近畿タンゴ鉄道の上限分離および運行会社の公募(WILLER社に選定)がありました。京都府を中心として沿線自治体の首長が議論に議論を重ね、鉄道存続および最適な運行事業者の公募という大きな決断があったからこそ、先進的なMaaS事例にまで発展したといえます。
また、熊本市では、熊本県・市が主導し、市域内で競合する路線バス事業者5社が共同経営を実施していく方針を打ち出しました。同一市域内で競合する5社が同じテーブルについて議論することさえ難しかった状況を変えたのは、県・市の将来の公共交通に対する危機感といえます。
さらに、松本市でも、新市長の方針により、地域の基幹的交通事業者であるアルピコ交通との間で、路線バスの公設民営化の議論が始まっています。従来は商業サービスと位置付けられてきた路線バスの公設化は、わが国の公共交通政策の大きな転換点になるかもしれません。
このように、社会の変容を受けて、地域自らが公共交通の役割や維持すべき公共サービス水準を再定義する動きが高まっています。このような取り組みこそ、真に持続可能なスマートシティ、つまりサステナブルシティにつながるものと考えられ、今こそ地域が公共交通の在り方を真正面から議論するときが到来しているといえるでしょう。


